機関紙「ほくだい」の2025年4月号に記事を投稿いたしましたので掲載いたします。
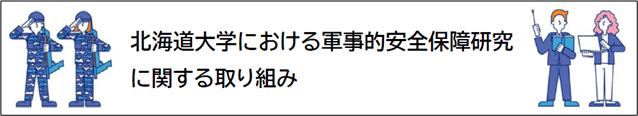
防衛装備庁が公募する安全保障技術研究推進制度に2024年度に北海道大学から2件の新規採択があったことが報道され注目を集めました。その一方で、国家プロジェクトとして軍事・防衛研究の一端を担っている制度に「経済安全保障重要技術育成プログラム(K Program)」というものがあります。この「K Program」には「民生・防衛目的が両立する技術の育成」が期待されており、それはその研究開発構想に「サイバー防御」「暗号技術」「小型無人機の自律制御」といった軍事技術に容易に転用可能なものが含まれることからも確認できます。本組合では複数の国立大学(筑波大学、名古屋大学、京都大学、等)がこのプログラムへの応募に対して大学による事前審査等を設けていることと、2024年10月時点において本学にそのような審査制度が無いことを確認した上で、本学における研究の健全性・公正性(研究インテグリティ)を確保するために本学においてもこのプログラムへの応募に対して事前審査制度を設けるよう、大学に対して2024年10月30日付けで要望書を提出しました。しかし大学は2025年3月27日に「当面は事前審査は不要」とする回答を本組合に対して行いました。その根拠として大学は、現時点で大学が事前審査を行うものはあくまで「国内外の軍事・防衛を所管する公的機関」からのものであり、K Programの配分機関となっているNEDOやJSTはこれに該当しないこと等を挙げました。
今回、北海道大学がK Program応募時の事前審査を否定したことを受けて本組合は、北海道大学における軍事的安全保障研究について一つの懸念を持ちました。それは「北海道大学は軍事研究を実施しないと言っているが、はたして北海道大学で実施できない軍事研究が本当にあるのだろうか」という懸念です。現状で北海道大学では、防衛装備庁の安全保障技術研究推進制度に対しては学内の研究インテグリティ委員会の審査を経ることで応募ができます。K Programに対してはそもそも無審査で応募でき、この体制を維持する意向であることも今回確認いたしました。日本においても重工業企業などを含む「軍需企業」は一定数存在しますが、それらとの共同研究に関しては部局決裁で締結ができ、全学的な審査制度がありません。外国の軍事機関や軍需企業からの契約についてはさすがに安全保障輸出管理等によるチェックがあるものの、少なくとも国内機関・国内企業との軍事的安全保障研究については民生技術を研究内容に0.1%でも入れれば研究を実施できると組合は理解しています。仮にこれが推測であったとしても、「審査制度有りと言えども防衛装備庁の研究助成制度への応募自体は可能」でさらに「K Programへの応募は無審査」である北海道大学が大学として国内で「最先端」の軍事的安全保障研究の実施体制を持っていることは確実です。 本記事では本学における軍事的安全保障研究実施の是非には触れません。しかし上記のような研究実施体制を持つ本学を仮に誰かが「軍事研究の北海道大学」と呼んだとして、それを明確に否定する材料は本学にはないように思われます。大学は「軍事研究をしない」と言っています。しかし、「黒を認めない」と公言しても、「黒に一滴の白を混ぜればそれは黒ではない」と言えるなら、それは実質的に黒を認めていると言わざるを得ません。
【参考報道】